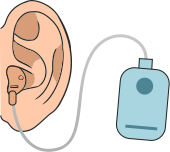- 「最近、会話が聞き取りにくい」「周りの音がこもって聞こえる」そんな悩みをお持ちではありませんか?年齢によっては耳の聞こえにくさを放っておくと、判断力の低下や、認知症・うつ病に繋がりやすいとの報告もあります。
補聴器の使用を“格好悪い”と感じる方もおられますが、これ以上聞こえにくさが進行する前に、早めに補聴器を使用し、ご家族や友人と快適な生活をおくりましょう。
聞こえでお悩みの方は、まずは耳鼻咽喉科を受診されることをおすすめいたします。 
【補聴器を買う前に】
耳鼻咽喉科で診断を受けましょう
- 補聴器は精密機器ですので、市販のものをそのまま使うのではなく、患者さんごとに機種の選択や調整が必要になります。医師の診断を受けずに補聴器を購入された方の中には、手術や薬による治療が必要な方、適した補聴器を装着されていない方もいらっしゃいます。
また、補聴器は決して安価なものではありません。
ご自身に合った補聴器を見つけるためにも、まずは耳鼻咽喉科で医師の診断を受けることを推奨いたします。 
補聴器は医療費控除の対象です
平成30年度から、補聴器購入に際し医療費控除が受けられるようになりました。医療費控除を受けるためには、以下の手順が必要となります。
補聴器医療費控除の手順
①補聴器相談医を受診し、問診・検査を受けます。
②補聴器相談医に「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」へ必要事項を記入していただき、受け取ります。
③補聴器販売店へ「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を提出し、補聴器の試用を行った上で補聴器を購入します。
※当院では木曜日の補聴器外来で手続きいたします
④「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の写しと補聴器の領収書を受け取り、当該年度の確定申告における医療費控除対象として申請し、保存してもらいます。
また、税務署からの求めがあった場合は写しと領収書を提出してください。
補聴器をご検討されている方は、当院までお気軽にご相談ください。
②補聴器相談医に「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」へ必要事項を記入していただき、受け取ります。
③補聴器販売店へ「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を提出し、補聴器の試用を行った上で補聴器を購入します。
※当院では木曜日の補聴器外来で手続きいたします
④「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の写しと補聴器の領収書を受け取り、当該年度の確定申告における医療費控除対象として申請し、保存してもらいます。
また、税務署からの求めがあった場合は写しと領収書を提出してください。
補聴器をご検討されている方は、当院までお気軽にご相談ください。
倉敷市では補聴器購入費の助成制度が受けられます
令和7年10月から、岡山県倉敷市にお住まいの方を対象とした助成制度が設けられました。補聴器購入費の2分の1(上限 25,000円)が、市から助成されます。対象要件・申請方法など、詳しくは市のホームページをご覧ください。
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/fukushi/elderly/1004318/1018238.html
耳の聞こえチェック
以下の項目に当てはまる方は、耳が聞こえにくい状態かもしれません。
気になる症状がある方は、一度耳鼻咽喉科で診断を受けましょう。
気になる症状がある方は、一度耳鼻咽喉科で診断を受けましょう。
- 会話しているときによく聞き返す
- 聞き間違えが多い
- 耳鳴りがある
- 後ろから呼びかけられたり、車が近づいてくる音に気付かないことがある
- 話し声が大きいと言われる
- 電子レンジの音や、ドアのチャイム音などが聞こえにくい
たち耳鼻咽喉科の補聴器外来について
- 補聴器のご相談をご希望の患者さんは、2回目以降から、専門の補聴器外来で診療いたします。
まずは一度通常の外来にお越しください。
当院では、毎週木曜日の午前中を補聴器外来としています。患者さんに合った補聴器を使用していただくために、専門のスタッフと共に1回30分程度かけて丁寧な調整を行っています。 
補聴器の相談の流れ
1.診断・検査
まずは耳の検査を行い、耳垢や中耳炎などが難聴の原因になっていないかをお調べします。その後に聞こえの検査を行い、補聴器が使えるかを確認します。2.補聴器の選択・試着
技能者立ち合いのうえ、補聴器を使う主な目的・シーンをお伺いして、補聴器の選定を行います。患者さんの聞こえに合わせた試着と調整を行い、2~4週間にわたり補聴器を貸し出してお試しいただきます。その際、補聴器の使い方なども丁寧にお伝えします。3.補聴器の点検・調整
再度ご来院いただき、補聴器の使用感や聞こえの具合についてをお伺いします。ご希望にあわせて補聴器の機種変更や再調整を行い、ご納得いただけるまでお試しいただきます。4.補聴器の選択・製作
ご納得いただける機種が見つかりましたら、製作を発注します。5.製作した補聴器の試着
補聴器は患者さんごとに製作しますので、お渡しするまでには時間がかかります。補聴器が届きましたら、調整を行い、お引き渡しさせていただきます。その際には、使い方やお掃除の仕方についてもご説明いたします。6.アフターケア
快適に補聴器をお使いいただくには、お引き渡し後も定期的にご来院いただきながら、小まめに調整やお掃除を行うことも大切です。日常生活のなかで気になることがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。補聴器の種類
補聴器は、大きく分けて「耳かけ型」「耳あな型」「ポケット型」の3種類があります。ご自身の聞こえの程度や目的、環境にあわせて選ぶことが大切です。
- 耳かけ型耳にかけて使用するタイプの補聴器は、操作が簡単で初心者にもおすすめです。耳裏に収まるため大きさが気になりにくく、閉塞感が少ないため長時間の使用も快適です。最近では、小型でカラフルなデザインやおしゃれなものも増え、見た目の選択肢も豊富です。
【軽度~高度の難聴まで対応】
また、レシーバー(スピーカー)が本体から分離し、耳の穴の中に収まるRIC(Receiver in Canal)タイプもあります。 
- 耳あな型耳の穴に収まるタイプの補聴器で、小型で軽量、目立ちにくいデザインが特徴です。イヤホンのような装着感があり、耳の集音機能を活かせる点も魅力です。耳の形状や聞こえの状態に合わせて作るオーダーメイドタイプが一般的です。
【軽度~中等度の難聴まで対応】
快適で自然な聞こえを求める方におすすめです。 
- ポケット型本体とイヤホンをコードで繋ぐタイプの補聴器です。スイッチやボリュームが大きく操作が簡単で、小型ラジオのように手元で扱える点が特徴です。マイク内蔵型の場合、話し手に本体を向けることでより聞き取りやすくなります。
【軽度~中等度の難聴まで対応】
また、一部のモデルでは、テレビや携帯電話、ドアホンと接続でき、クリアな音声での聞き取りが可能です。 
補聴器と集音器の違いとは?
- 集音器は一般的な音響機器である一方、補聴器は厚生労働省が定めた基準を満たし、医療機器として認定されています。
また、補聴器の使用には聴力検査や聴力に合わせた音の増幅調整が必要です。そのため、補聴器を購入する際は、補聴器相談医に相談し、適切なフィッティングを行うことが推奨されます。
当院では、補聴器が自分に合っているかをじっくり試していただけるよう、1カ月間の無料お試し貸し出し期間をご用意しています。十分に納得した上で、購入をご検討いただけます。 
補聴器を持っているのにうまく使えない方へ
「補聴器を購入したものの、うまく使えない…」とお悩みの方は、実は多くいらっしゃいます。補聴器が合わない、または使用が難しいと感じる原因として、次のようなケースが考えられます。補聴器そのものに問題がある場合
補聴器は精密機器のため、定期的なメンテナンスが欠かせません。長期間メンテナンスをしないと、不具合が発生することがあります。また、補聴器が緩んだり変形したりすると、外れやすくなったり、使いにくくなる場合もあります。耳の状態に問題がある場合
たとえば中耳炎にかかっていると、補聴器に異常がなくても聞こえにくくなることがあります。また、耳垢が溜まっているだけでも聞こえが悪くなることがあるのです。 当院では、補聴器本体の問題と耳の状態、それぞれを適切に検査し、
原因を突き止めます。
「補聴器を持っているけれど使いこなせない」と
お困りの方も、ぜひお気軽にご相談ください。
原因を突き止めます。
「補聴器を持っているけれど使いこなせない」と
お困りの方も、ぜひお気軽にご相談ください。

 初診の方はまずはこちらをご覧ください
初診の方はまずはこちらをご覧ください