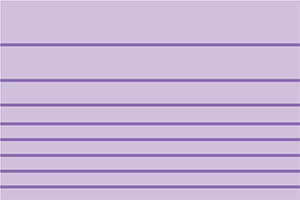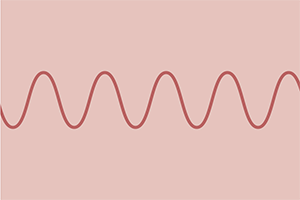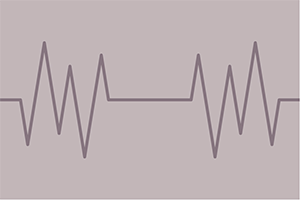「耳鳴りかな?」と思ったら、早めのご相談をおすすめします。
- 実際には音がしていないのに、「キーン」や「ジー」といった音が耳や頭の中で聞こえる…。そんな状態を「耳鳴り」といいます。
気圧の変化などで一時的に耳鳴りを感じることは、どなたにもあることで、心配はいりません。でも、その音が長く続いたり、生活に支障を感じるほどになってきたら、治療が必要なサインかもしれません。
耳鳴りの原因はさまざまで、加齢や大きな音、筋肉のけいれん、体の病気などが関係していることがあります。また、ストレスや疲れ、寝不足が引き金になるケースもあります。 
「ずっと音が鳴っている」「しばらく良くなったと思ったのにまた鳴り始めた」など、感じ方は人によってさまざま。周りの人には伝わりづらい症状だけに、ご本人にとってはとてもつらいものですよね。
耳鳴りの原因をきちんと調べて、その方に合った治療を行うことで、症状の改善が期待できます。「これって耳鳴り?」「なんだか耳が変…」そんな時は、どうぞお気軽に当院までご相談ください。
当院の耳鳴り外来について
詳しくはこちら
耳鳴りの種類と原因
耳鳴りにはいくつかのタイプがあり、どんな音が聞こえるかは、その原因によって少しずつ違ってきます。
メニエール病や突発性難聴、加齢による難聴など、耳の病気が原因になっていることもあります。また、高血圧や動脈硬化、心臓の病気など、全身の健康状態が関係しているケースも。
特にメニエール病では、耳鳴りのほかに「ぐるぐるとしためまい」や「吐き気」を感じることもあります。
めまいについて 詳しくはこちら
- 「キーン」「ピー」などの高音の耳鳴り金属音のような「キーン」、電子音のような「ピー」など、高い音が耳の中で鳴っているように感じることはありませんか?こうした高音の耳鳴りは、睡眠不足や疲れ、ストレスがたまったときに起こりやすいといわれています。
これは、耳の中の音を感じる仕組みに一時的に血流が足りなくなることで起こると考えられていて、多くの場合はしばらくすると落ち着くことがほとんどです。でも、続いたり繰り返したりするようであれば、注意が必要です。 
メニエール病や突発性難聴、加齢による難聴など、耳の病気が原因になっていることもあります。また、高血圧や動脈硬化、心臓の病気など、全身の健康状態が関係しているケースも。
特にメニエール病では、耳鳴りのほかに「ぐるぐるとしためまい」や「吐き気」を感じることもあります。
めまいについて 詳しくはこちら
- 「ゴォー」「ザー」などの低音の耳鳴り低音域の「ザー」や「ゴー」といった音が耳の中で響いているように感じる場合、急性中耳炎や滲出性中耳炎といった耳の感染症が原因になっていることがあります。
また、耳あかがたまって耳の通り道をふさいでしまう「耳垢栓塞(じこうせんそく)」や、音の伝わりにくさが原因となる「耳硬化症(じこうかしょう)」「耳管狭窄(じかんきょうさく)」などの病気が関係していることもあります。
こういったケースでは、耳鳴りのほかに「自分の声が響いて聞こえる」といった違和感が出ることも。 
- 「ブクブク」「ポコポコ」などの不定期かつ一定のリズムで聞こえる耳鳴り耳のまわりや、耳の奥にある小さな骨(耳小骨:じしょうこつ)を動かす筋肉がピクピクとけいれんすることで、音が聞こえることがあります。
実際には外から音は出ていないのに、自分にはハッキリと聞こえる——そんな耳鳴りの一種です。
このタイプの耳鳴りは、筋肉の動きが関係しているため、一定のリズムで鳴ることが多いのが特徴です。 
- 「ガサガサ」「ゴソゴソ」などの乾いた音の耳鳴り耳の中で「ガサガサ」や「ゴソゴソ」といった、まるで何かが動いているような乾いた音が聞こえることがあります。
このような耳鳴りは、耳の奥にたまった耳あかが原因だったり、まれに小さな虫が耳に入ってしまっているケースもあります。 
- 「シャー」「ドクドク」「ドコドコ」などの持続する拍動性の耳鳴りこうした音の原因には、脳の血管に関係する異常が隠れていることもあります。
たとえば、脳梗塞や脳出血の前ぶれ、あるいは脳腫瘍によって血管が圧迫されている可能性も否定できません。
特に、「ドクドク」といった脈打つ音がはっきり聞こえるときには、耳の病気よりも脳神経系の精密な検査(MRIなど)が必要なケースもあります。 
- 片耳から聞こえる耳鳴り片耳からだけ耳鳴りが聞こえるとき、それは突発性難聴やメニエール病、聴神経腫瘍など、耳や音を感じる神経に何らかの異常が起きているサインかもしれません。
最近では、イヤホンやヘッドホンで音楽を大きな音で長時間聴くことで起こる「音響性難聴(ヘッドホン難聴)」が原因になるケースも増えています。
ライブやコンサートなど、大音量の環境に長くいることで耳に負担がかかり、あとから耳鳴りを感じることもあるため、注意が必要です。 
- 両耳から聞こえる耳鳴り左右どちらの耳からも同時に耳鳴りが聞こえるようなときは、加齢による聴力の変化(老人性難聴)や、長時間の大きな音による耳への負担(騒音性難聴)が関係していることがあります。
たとえば、工事現場や工場など、音の大きな環境で長く働いている方に見られることが多く、耳がじわじわとダメージを受けた結果、耳鳴りが続いてしまうことがあるんです。
また、高血圧や腎臓の病気といった体の不調が、両耳の耳鳴りにつながるケースもあります。
「耳が鳴るだけ」と思わずに、体のサインとしてとらえてあげることも大切です。 
たち耳鼻咽喉科の
耳鳴り外来について
耳鳴りの治療をご希望の患者さんは、まずは一度通常の外来にお越しください。
2回目以降から、専門の耳鳴り外来で診療いたします。
当院では、毎週木曜日の午前中を耳鳴り外来としています。
慢性的な耳鳴りに悩まされている方に対して、当院ではただお薬を出すだけでなく、
じっくりとお話をお聞きしながら、その方に合った改善方法を一緒に探していきます。
当院の診療時間表はこちら当院では、毎週木曜日の午前中を耳鳴り外来としています。
慢性的な耳鳴りに悩まされている方に対して、当院ではただお薬を出すだけでなく、
じっくりとお話をお聞きしながら、その方に合った改善方法を一緒に探していきます。
当院では、以下の内容を中心に、患者さんお一人おひとりの症状にあわせた診療を行っています。
- 睡眠時間や食事などの生活の改善指導規則正しい生活を心がけ、体調を整えることは耳鳴りの改善にもつながります。栄養バランスのとれた食事を意識し、しっかりと睡眠時間を確保することが大切です。
特に、軽い耳鳴りの場合は、疲れや睡眠不足を解消するだけで症状がやわらぐこともあります。体をゆっくり休めて、無理のない毎日を送ることが、耳の健康にもつながっていくかもしれません。 
- 薬物療法耳鳴りには原因がはっきりしないこともありますが、もし耳鳴りの元となっている病気が見つかった場合は、まずその病気の治療をしっかり行っていきます。お薬による治療では、耳鳴りの原因にアプローチするもののほかに、ストレスや不安など、心の負担をやわらげるためのお薬を使うこともあります。
たとえば、炎症をおさえるステロイド剤、内耳の血流をよくする血管拡張薬、神経の働きを助けるビタミン剤などが用いられます。また、ストレスや不安が強い方には、抗不安薬や抗うつ薬、眠りを助ける睡眠導入剤などがサポートとして処方されることもあります。
治療の選択肢はいろいろありますので、まずはご自身の状態をしっかり把握することが大切です。 
- 音響療法まずはカウンセリングを通して、耳鳴りについての正しい知識を身につけていただき、ご自身の状態をしっかり理解してもらうところから始まります。そのうえで、「音響療法」と呼ばれるステップへと進みます。
私たちは普段、すべての音を同じように意識しているわけではありません。たとえば、時計の「カチカチ音」や冷蔵庫の「ブーン」という音など、聞こえていても気にしていない音ってありますよね。 
音響療法は、この“無意識に音をスルーする”脳の仕組みをうまく使って、耳鳴りも「気にならない音」として慣れていくことをサポートする治療です。専用の装置を使って、耳鳴りが聞こえるくらいのごく小さな音を1日6~8時間ほど流しながら生活していただきます。
効果が現れるまでの期間は個人差がありますが、半年〜2年ほどかけて、少しずつ改善を目指していきます。
- 聞こえの程度によって「補聴器」を使用耳鳴りに悩まれている方の中には、実は軽い聴力の低下が関係しているケースも少なくありません。その場合、補聴器を使うことで「耳鳴りが気にならなくなった」と感じる方も多くいらっしゃいます。
当院では、聞こえの程度やライフスタイルに合わせて、最適な補聴器のご案内をさせていただいています。「補聴器ってどんなもの?」「試してみたいけど不安…」という方も、まずはお気軽にご相談ください。 
症状に応じて他の科の先生への紹介
耳鳴りの原因が耳以外にある可能性があると判断される場合には、脳神経外科や心療内科など、他の専門医をご紹介することもあります。当院では、耳だけでなく全身の状態や心のケアも含めた、総合的なサポートを大切にしています。当院では
患者さんの症状にあわせた
診療を行っています
耳鳴りは、音の感じ方や原因、症状の現れ方も人それぞれ。
だからこそ、ひとつの治療法だけでなく、体や心の状態に合わせたサポートが大切です。
お薬や音響療法、補聴器の活用、生活習慣の見直しなど、当院ではさまざまな角度から耳鳴りの改善をサポートしています。
また、必要に応じて他の専門の医師と連携をとりながら、患者さんお一人おひとりに合った治療を一緒に考えていきます。
だからこそ、ひとつの治療法だけでなく、体や心の状態に合わせたサポートが大切です。
お薬や音響療法、補聴器の活用、生活習慣の見直しなど、当院ではさまざまな角度から耳鳴りの改善をサポートしています。
また、必要に応じて他の専門の医師と連携をとりながら、患者さんお一人おひとりに合った治療を一緒に考えていきます。
「気のせいかも」と思って放っておくのではなく、
少しでも不安なことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。
少しでも不安なことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。

 初診の方はまずはこちらをご覧ください
初診の方はまずはこちらをご覧ください